障害者雇用で、こんな悩みはありませんか?
- 採用時や入社後に合理的配慮を申し出られ、「これは本当に必要なのか?」と疑問に感じる
- 配慮をしているつもりでも、周囲から”特別扱い” ”わがまま”と受け取られていないか心配になる
- 合理的配慮の具体的な進め方が分からず、対応がぎこちなくなってしまう
特に精神・発達障害のある方の雇用に取り組む企業では、こうした悩みがよく聞かれます。
その背景には、「合理的配慮=わがまま」という根強い誤解が存在している場合も少なくありません。
本記事では、この誤解を解消し、障害者雇用を円滑に進めるための具体的な対策を3つの視点から解説します。
このページの目次
1.「合理的配慮=わがまま」は誤解!制度理解不足がトラブルの原因に
2.誤解が引き起こす職場の問題とは?
3.誤解を防ぎ合理的配慮をスムーズに進める3つの解決策
【課題1】制度の理解不足
【課題2】対話の仕組みがない
【課題3】職場とのミスマッチ
4.実例:合理的配慮がチーム全体に好影響を与えたケース
まとめ:合理的配慮は「調整」であり「対話」がすべて
「発達障害の特性に対する合理的配慮 対応事例集」無料公開中
発達障害のある方への合理的配慮の実例をまとめた対応事例集です →(無料) ダウンロードはこちら
1.「合理的配慮=わがまま」は誤解!制度理解不足がトラブルの原因に
「合理的配慮」とは、障害者差別解消法などに基づく企業の義務であり、障害のある方が他の社員と同じように働けるように行う「業務上の調整」です。
本人からの申し出を基本とし、企業側が過重な負担とならない範囲で検討・対応するものです。
決して、企業が一方的に与えるものでも、本人が過剰に求めるものでもありません。
制度の正しい理解がないまま支援を行うと、次のような誤解が生まれがちです。
| 誤解 | 背景・原因 | 正しい認識 |
| 特別扱い・わがまま? | 障害者だけ優遇されているように見える | 障害者が対等に働くために必要な対応 |
| 配慮は善意や気遣い? | 「配慮」という言葉が曖昧で誤解されがち | 法的義務に基づく合理的な「業務調整」 |
| バリアフリーと同じ? | ユニバーサルデザインと混同しがち | 本人の困りごとに応じた「個別対応」が必要 |
| 本人が何も言わない=問題なし | 配慮を言い出しにくい状況、または周囲に困っていることを気づかれていない | 対話や気づきの仕組みづくりが重要 |
2.誤解が引き起こす職場の問題とは?
合理的配慮への誤解を放置すると、以下のような問題が職場に発生しやすくなります。
- 本人の孤立と不安の増大
支援を求めることへの遠慮や不安により、必要な調整が行われず孤立感が深まる - 自立心を損なう可能性
過剰なサポートにより、本人が本来持っている力を発揮する機会が奪われ、自信喪失につながる - 社内の不満・不和の発生
「理由不明の特別対応」に見えることで、他社員の不公平感が生じる - 早期離職による定着率低下
働く環境に馴染めず退職につながる
こうした事態は、制度があっても「正しく伝わっていない」「運用されていない」ことが原因で起こります。
「発達障害の特性に対する合理的配慮 対応事例集」無料公開中
発達障害のある方への合理的配慮の実例をまとめた対応事例集です →(無料) ダウンロードはこちら
3.誤解を防ぎ合理的配慮をスムーズに進める3つの解決策
誤解の背景には、主に次のような課題があります。それぞれに対して有効な対策をご紹介します。
【課題1】制度の理解不足
関係者が「合理的配慮=業務の調整」であるという制度の本質を正しく理解していないと、判断がぶれたり過剰・不足の対応になったりします。
▶ 解決策
- 研修を通じて、「合理的配慮は企業の義務」であり、障害のある社員が力を発揮するための「業務調整の一部」として理解を深める
- 「何が分からないのか」「どこまで配慮するべきか」「本人がどんな工夫をしているか」を明確にして、整理する
【課題2】対話の仕組みがない
合理的配慮は、制度だけでは機能しません。話しやすい環境と継続的な対話の仕組みが必要です。
▶解決策
- 初期面談で丁寧なヒアリングを行う
- チャットツールやアンケートなど、話しやすい手段を用意する
- 1on1や定期面談で継続的な対話の場を設ける
- 支援機関スタッフやジョブコーチの同席により、心理的な安心感をつくる
【課題3】職場とのミスマッチ
配属先の環境や業務内容が合わない場合、配慮が活かされにくくなります。
▶ 解決策
- 入社前に職場体験・実習を行い、相互理解を深める
- 入社後も業務や環境の調整を継続する
4.実例:合理的配慮がチーム全体に好影響を与えたケース
Aさんは「会議中の情報量が多く整理がしきれずに混乱する」という悩みを抱えていました。
そこで、議題を事前共有する合理的配慮を希望し、企業側は受け入れました。
その結果、チーム全体の準備意識が高まり、議論の質も向上していきました。
このように、合理的配慮は本人のためだけでなく、組織全体の業務改善にもつながる可能性があります。
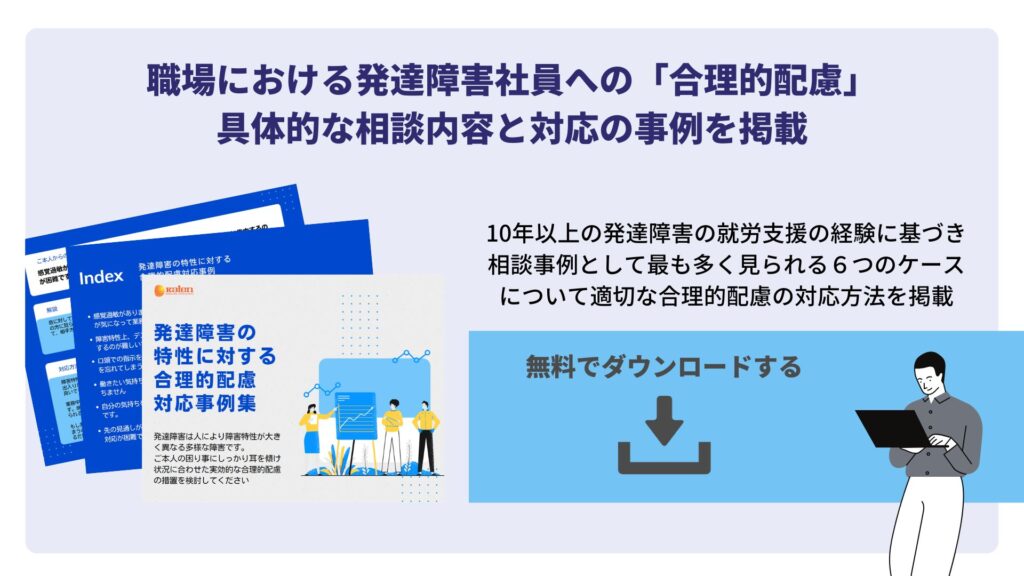
まとめ:合理的配慮は「調整」であり「対話」がすべて
合理的配慮とは、障害のある社員が、他の社員と同じように働くための「業務上の調整」であり、”わがまま”ではありません。
制度としての理解、対話の継続、さらに職場とのマッチングがそろうことで、合理的配慮は「誰もが働きやすい職場づくりの一環」として浸透します。
実際に、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者の雇用の実態等に関する調査研究」(2024年3月)では、精神障害のある社員が適切な配慮を受けている場合、業務継続の意欲が高まるという結果も出ています。
合理的配慮の誤解を解き、制度を正しく運用することで、障害のある社員を「特別な存在」ではなく、共に働く仲間として受け入れられる環境を整えませんか。
貴社の障害者雇用に関する支援・ご相談はこちら
株式会社Kaienでは、合理的配慮の理解・運用促進など、さまざまな障害者雇用に関するお悩み相談をお受けしています。
「合理的配慮についてどこまで対応すればいいのか」
「精神・発達障害のある方の雇用がうまくいかない…」
「受け入れ体制に不安がある」
上記のようなお悩みがございましたら、私たち専門スタッフにお気軽にご相談ください。
貴社の課題に応じた実践的なアドバイスとサポートをご提供いたします。
【無料相談】現場での悩みに専門スタッフが対応します
【メルマガ登録】障害者雇用に役立つノウハウや事例を定期配信しています

