6月1日時点での障害者雇用状況を報告する「ロクイチ報告」に向けて、精神障害者の採用を行った企業も多いことと存じます。採用目標を達成し、ほっとしたのも束の間、下記のような不安や葛藤を抱えているご担当者様は少なくないのではないでしょうか。
「障害のある社員が早期に離職してしまわないか不安…」
「フォロー体制が整っておらず、現場任せになってしまっている」
このようなお悩みは、まさに障害者雇用における「離職」の大きな「課題」であり、多くの企業担当者様が直面していることでしょう。
本記事では、早期離職の主な原因である「認識のギャップ」を解消し、精神障害のある方が安心して長く働ける職場を築くための4つの具体的な対策を、事例を交えながら詳しく解説します。
このページの目次
- 精神障害者雇用の定着率は依然として低い
- なぜ精神障害者の離職は多いのか?雇用後に生じる「認識のギャップ」が根本原因
- 【実践策】障害者雇用の離職課題を解決する!今からできる4つの対応ポイント
- ポイント1:精神障害者雇用成功の土台!丁寧なオンボーディングと「心理的安全性」を育む情報共有
- ポイント2:定着を促す!個別の「合理的配慮」と誰もが働きやすいを取り入れた職場環境整備
- ポイント3:「チームで支える」文化を醸成!全社員で取り組む「巻き込み型」コミュニケーション
- ポイント4:専門家の力を借りる!福祉のプロ「就労定着支援事業」活用で離職リスクを軽減
- まとめ:離職防止対応は「チーム戦」。ひとりで抱え込まないで
「発達障害の特性に対する合理的配慮 対応事例集」無料公開中
発達障害のある方への合理的配慮の実例をまとめた対応事例集です →(無料) ダウンロードはこちら
1. 精神障害者雇用の定着率は依然として低い
まずは、障害者雇用における「離職」の課題、特に精神障害のある方の定着における現状を、客観的なデータから見てみましょう。厚生労働省の資料(令和7年6月10日)によると、精神障害者の1年後の職場定着率は50%前後と、他の障害種別(身体・知的)と比較して依然として低い水準にあります。
参考) 厚生労働省「 第6回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会 事務局説明資料」より引用
このデータは、多くの企業が精神障害者の雇用定着に課題を感じている現状を示唆しています。平成30年の精神障害者の雇用義務化以降、採用数自体は増加していますが、採用時の見極め不足や雇用後の課題により、離職に至るケースが後を絶ちません。
2. なぜ精神障害者の離職は多いのか?雇用後に生じる「認識のギャップ」が根本原因
精神障害のある方の早期離職の理由として特に多いのが、障害のある社員と職場との認識のギャップです。
企業側の認識と、障害のある社員本人の認識が噛み合わず、互いに「こんなはずではなかった」と感じてしまうことに起因します。このすれ違いこそが、離職防止を阻む大きな要因となっています。
【ギャップの例】
| 企業側の認識・期待 | 障害のある社員側の認識・実態 | |
| 業務内容・スキル | 「この業務ならできるだろう」「これ位のスキルはあるはずだ」 | 「想定していた仕事と違う」「自分のスキルを活かせない」「業務レベルが高すぎる」 |
| 障害への配慮 | 「配慮はしているつもりだ」「これ以上の配慮は難しい」 | 「必要な配慮をしてもらえない」「過剰な配慮でかえって働きづらい」 |
| 労働条件・環境 | 「提示した条件で問題ないだろう」 | 「給与・勤務時間・通勤方法が実状と合わない」「職場の騒音や人間関係が辛い」 |
| 社風・文化 | 「当社の文化に馴染んでほしい」 | 「職場の雰囲気に馴染めない」「孤立感を感じてしまう」 |
こうしたギャップは、早期離職の原因となるだけでなく、本人の自信喪失やモチベーション低下を招き、結果として職場全体の負担増にもつながりかねません。
採用時の見極めに課題がある場合もありますが、今からでも離職防止のためにできる対応方法はあります。
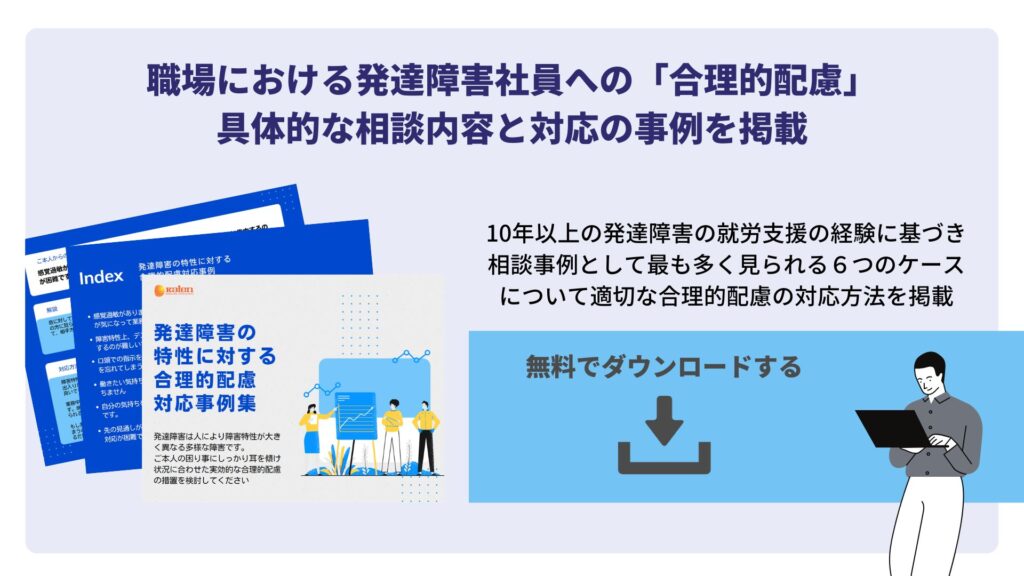
3. 【実践策】障害者雇用の離職課題を解決する!今からできる4つの対応ポイント
では、こうした認識のギャップを乗り越え、離職を防ぐためには、具体的に何をすればよいのでしょうか。ここからは、明日から実践できる4つの対応ポイントを詳しく解説します。
ポイント1:精神障害者雇用成功の土台!丁寧なオンボーディングと「心理的安全性」を育む情報共有
精神障害のある方にとって、新しい環境への適応は大きなエネルギーを要します。入社前から入社後にかけて、丁寧なサポートを継続することが重要です。
- 採用段階でのすり合わせ:業務内容や職場環境を具体的に伝え、本人が希望する配慮と会社が提供できる配慮をすり合わせる。
- 余裕のあるオリエンテーション:入社後は一度に多くの情報を伝えず、本人のペースに合わせて情報量を調整する。
- 「相談先」の明確化:困ったときに、誰にどのように相談すればよいかを具体的に伝えておく。
- OJT中の定期的な声かけ:最初はできる限り期限に余裕のある業務でスキルを測る。放置せず、定期的に1対1で話す機会を設け、不安や課題を早期にキャッチする。
「ここなら、安心して働けそう」という見通しが立てられる、心理的安全性を保つことが離職防止の土台になります。
ポイント2:定着を促す!個別の「合理的配慮」と誰もが働きやすいを取り入れた職場環境整備
精神障害は外見から分かりにくいため、一人ひとりの特性に合わせた個別性の高い合理的配慮が求められます。同時に、「誰にとっても働きやすい環境」を整えることで配慮が行き渡りやすくなります。
- 合理的配慮の例:
- 通勤方法:在宅勤務のルールを決め、心身のバランスを整えやすいよう調整を行う。
- 業務内容:強みを活かし、成長に繋がるような業務アサインを行う。
- 誰もが働きやすい環境整備の例:
- 集中して作業できる静かなスペースを用意する。
- 業務指示はマニュアルなどを用いて目に見える形で行う。
合理的配慮は、本人、職場、社会の変化に合わせて、内容を見直す必要があります。対話を継続することが重要です。
ポイント3:「チームで支える」文化を醸成!全社員で取り組む「巻き込み型」コミュニケーション
合理的配慮を機能させるには、配属先の上司や同僚の理解と協力が不可欠です。担当者任せにせず、チーム全体で支える仕組みをつくりましょう。
- 障害理解研修の実施:管理職や現場社員向けに、障害特性や適切な関わり方について学ぶ研修機会を設ける。
- 情報共有ルールの明確化:本人の同意のもと、配慮に必要な情報を誰にどこまで伝えるかを事前に決めておく。
- 共通認識の醸成:配慮のポイントを共通認識として持つことで、「特別扱い」ではなく「チームとして支え合う」という文化を育む。
関連部署の役割を明確にし、情報共有を図ることで、チーム全体で支える仕組みが構築できます。これは本人のサポートだけでなく、担当者や職場全体の負担軽減にもつながります。
ポイント4:専門家の力を借りる!福祉のプロ「就労定着支援事業」活用で離職リスクを軽減
企業単独での離職防止の対応を行うには限界もあります。福祉の専門機関が提供する「就労定着支援事業(※)」などを活用することで、職場・障害のある社員双方の負担を大きく軽減できます。
- 専門家による定期面談:本人の悩みや不安を専門家がヒアリングし、サポートする。
- 企業への客観的な助言:職場環境の改善や本人との関わり方について、専門的な視点からアドバイスがもらえる。
- トラブルの予防と早期解決:職場での対人関係トラブルなどを未然に防ぎ、問題が起きても間に入って調整してくれる。
※就労定着支援事業:障害のある方が働き続けられるよう、専門の支援員が本人と企業の間に立ち、定期的な面談や助言を行う公的な福祉サービスのこと。
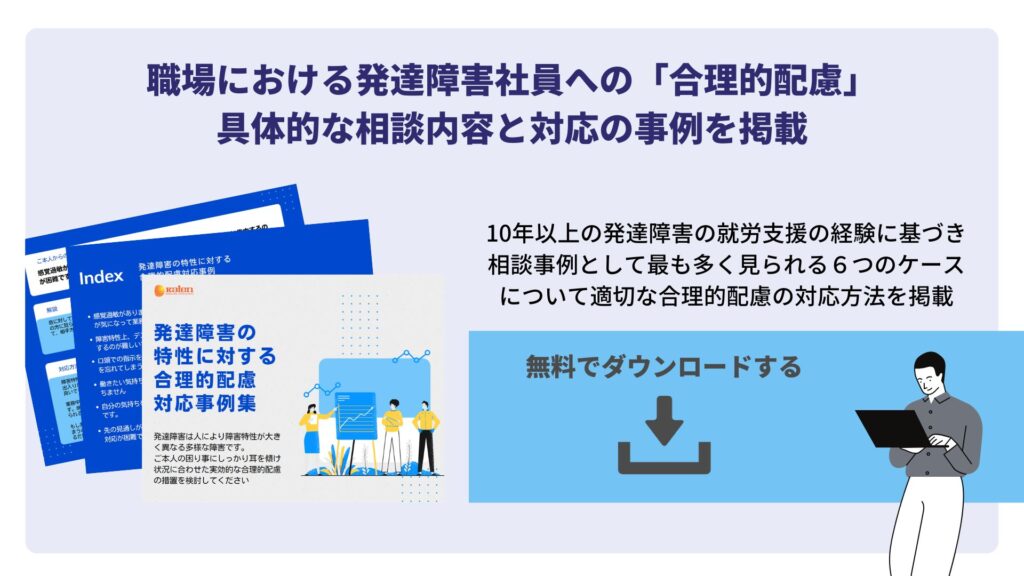
4. まとめ:離職防止対応は「チーム戦」。ひとりで抱え込まないで
本記事では、障害者雇用における「離職」という課題を解決し、精神障害のある方の早期離職防止と職場定着を実現するための4つの重要なポイントについてご紹介しました。
障害者雇用における離職防止の取り組みは、決して一人の担当者が抱え込むべきものではありません。まさしく「チーム戦」です。大切なのは、現場の上司や同僚、そして外部の専門機関と連携し、会社全体で支える体制を築くことです。
障害のある社員の安定した雇用は、本人と職場が信頼関係を築き、相互理解を深めた先にこそ実現します。貴社が抱える障害者雇用の課題を解決し、新しく迎えた仲間が安心して長く働ける環境を、チーム一丸となって整えていきましょう。
Kaienでは、上記の「就労定着支援事業」を含め、精神障害者雇用に関する総合的なサービスを展開しています。まずは専門家にお問合せください。
ご相談は無料です、まずは気軽にご連絡ください
障害者雇用に関するお役立ち情報はこちらから

